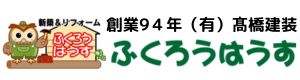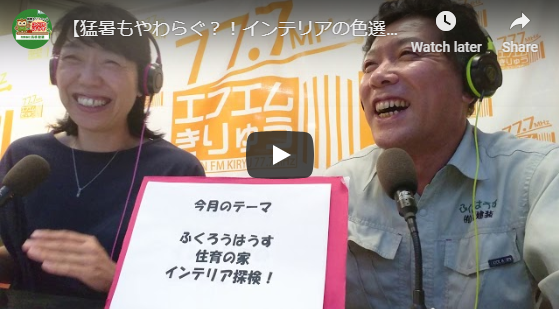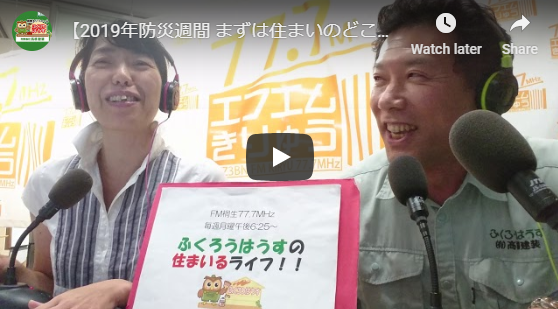毎年9月1日の「防災の日」は、
改めて地震や災害への備えを考える日です。
災害はいつ起きるか分かりません。
だからこそ、日頃から家の安全性を
見直しておくことが大切です。
今回は、「防災の日」にちなんで、
前回に引き続き、
阪神淡路大震災後に見えてきた、
建物の“強さ”を分けるポイントについて
お話しします。

倒壊の原因は「足元」にあった
阪神淡路大震災後、私は東灘区などで、
多くの古い建物を目にしました。
築100~150年、それ以上の年数の家の中には、
倒壊してしまったものもあれば、
驚くほど無傷で残っているものもありました。
その違いは、見た目ではなく
土台の状態にありました。

直下型地震は、縦に突き上げられた後、
横にずれる動きが加わります。
このとき土台がしっかりしていないと、
柱ごと“すっぽ抜けて”
横に倒れてしまうのです。
実際、倒壊した建物の多くは、
土台が不完全なまま補修されていたり、
そもそも修理されていなかったり
というものでした。
逆に、同じ築200年の家でも、
土台が丁寧に直され、
柱がしっかり固定されている家は、
重い土葺き屋根をのせながらも
倒れませんでした。
足元が安定していることで、
横揺れや縦揺れの力を上手く吸収できるのです。
昔の大工の「手加減」の技
現代の耐震設計は数値化が基本ですが、
昔の大工は一軒一軒違う家に合わせて、
木の特性や曲がり、ねじれを活かし、
力を逃がす工夫をしていました。
松の梁が曲がっているのも、
ただの欠点ではなく
「しなり」や「分散」のため。

弱めるべきところはあえて弱く、
固めるべきところはしっかり固める
そんな絶妙なバランス感覚が生きていたのです。
素材を見極める目が家の寿命を延ばす
家を見ていると、
「どう工夫して、どこを直せばいいのか」
という“勘どころ”が見えてきます。
竹小舞や通し貫など、昔からの部材は、
その素材の特性まで計算し尽くされていて、
どれ一つ無駄なものはありません。
竹小舞は、竹を十文字に編んで、
井桁(いげた)にして、土をかぶせて
塗り込んで壁を作っていきます。
通し貫は、柱や束などの垂直部材に、
穴を空けて、水平に貫通させる工法で、
竹小舞を取り付けるための補強材となります。
お客様がよく心配されるのは、
「古くて何十年も経っているけど大丈夫?」
ということです。
でも、古いからといって、
必ずしも劣化しているわけではありません。
例えば、竹小舞は、切る時期や乾燥の仕方、
水にさらす工程などによって、
耐久性が大きく変わります。
昔の職人はその一つひとつを丁寧に見極め、
長く持つように工夫していました。

素材を見れば「あと40~50年は持つ」
と判断できるものも多くあります。
中には雑な作りで
耐久性が落ちているものもありますが、
総じて、昔の家は百年住宅を見越して
造られていました。
かつては、
「孫やその先の世代まで暮らせるように」
そんな思いを込め、
山から木を切り出し、時間をかけて磨き上げて、
家を建てるのが当たり前でした。
このように作られた家は、適切に手を入れれば、
今も十分に活かすことができます。
バランスを崩すと耐震性は下がる
熊本地震の事例では、
現代風に再現された伝統工法の家が
倒壊していました。
その原因は「逃げ場」をなくしたこと。
耐震性を高めようとして、
本来は柔らかくすべき部分を硬くしてしまい、
地震の力が集中して破損してしまったのです。
一方、手を入れすぎず、バランスを保った家は、
震度6強が連続で来ても倒れませんでした。
家の寿命は床下と天井裏に現れる
床下と天井裏を見れば、
その家の寿命や施工の質がほぼわかります。

基礎から柱、梁、屋根まで、
すべてが力を分散しあって成り立つのが家。
だからこそ、地震に強い家づくりには
「計算だけでは出せない職人の感覚」と
「足元から整える修理」が欠かせません。
地震に耐える家は、
単に“強く”造ればよいわけではありません。
力を逃がす場所と受け止める場所、
そのバランスを見極める目と技。
つまり、昔の大工の知恵と素材を見る目が、
今も私たちの住まいを守る鍵になっています。
国の補助金・桐生市の住宅リフォーム補助金の活用サポートはこちら
「ふくろうはうすの住まいるライフ」(FM桐生毎週水曜日12:40分~)はこちら
YouTube チャンネル「ふくろうはうすの住まいるライフ」はこちら
群馬県桐生市の工務店
リフォーム・リノベーション専門店
住まいの健康寿命診断士
ふくろうはうす(高橋建装)の高橋でした。
次回は「山用品が防災用品に?意外な備えの工夫」
のテーマで準備しています。
楽しみにしてくださると嬉しいです。